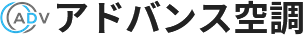
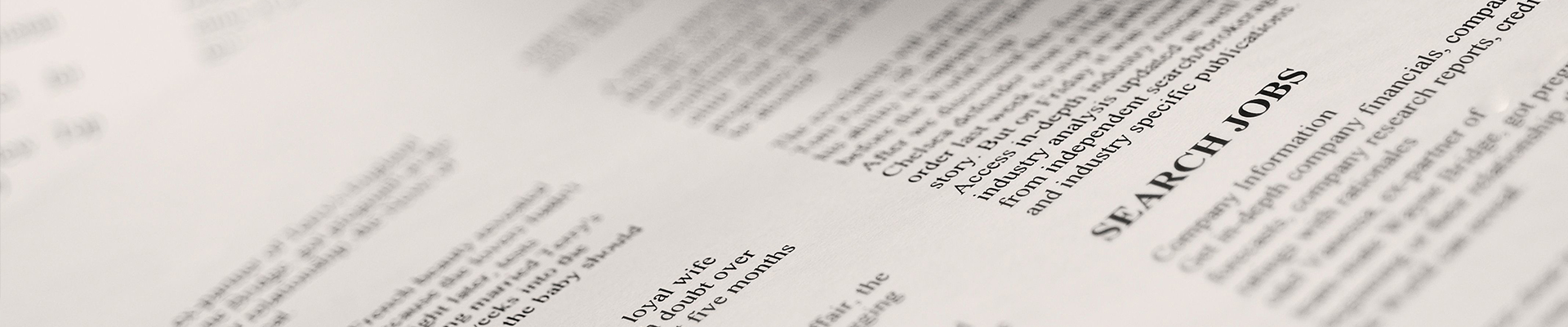
ゼロエミッションで補助金を活用しませんか?
東京都「ゼロエミッション補助金」でエアコン更新を賢く!知っておきたいポイントと活用方法
東京都が掲げる「2050年CO₂実質ゼロ」の実現に向けて、空調設備を含む省エネ機器の導入を支援する補助制度が充実しています。店舗・オフィス・事務所など“業務用”の空調機器を更新検討中の事業者にとっても、大きな機会です。本記事では、東京都の代表的な補助制度を「エアコン・空調設備」視点で解説。制度内容・対象・申請の流れ・活用のコツまでわかりやすくまとめました。
1. なぜ今、エアコン更新に“ゼロエミ”補助金が注目されるのか?
東京都では、空調・照明・変圧器などエネルギー使用量の大きな設備を更新・運用改善することで、温室効果ガス(CO₂)の削減を加速させようとしています。
例えば、家庭用・業務用問わず、冷暖房設備は建物のエネルギー使用の大きな割合を占めるため、効率の良い機器に更新することで即効的な省エネ・CO₂削減が期待できます。juutakuseisaku1.metro.tokyo.lg.jp+1
その流れの中で「空調設備(エアコン)の更新」が補助対象となっており、導入タイミングの好機といえます。
2. 主な補助制度とその概要
「ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業」
こちらは主に「事業者/中小企業等」の省エネ設備導入・運用改善を支援する制度で、空調設備も対象に含まれています。
-
対象設備の中に、高効率空調設備(=エアコン・空調システム)があります。東京都交通局+1
-
助成率・上限額として、例えば令和6年度は助成率2/3、上限2,500万円(※条件によって)という情報があります。
-
令和7年度には、予算規模が約86.7億円に拡大予定など、制度の活用機会が増えています。
-
申請の受付期間(例:第1回令和7年4月23日~5月9日)も公表されています。東京CO2ダウン
この制度は「事業用途」での空調システム更新/運用改善に直結するため、店舗・オフィス・工場などのエアコン交換時には最も有力な選択肢のひとつです。
3. 補助制度を活用する際のチェックポイント
制度を活かすために押さえておきたいポイントを整理します。
✅ 対象設備・対象者を確認
-
例えば、事業者向け制度では「中小企業・学校法人・医療法人・社会福祉法人等」が対象です。東京都交通局+1
-
「高効率空調設備」が対象設備に明記されています。東京都交通局+1
-
家庭用制度では、買替対象機器の「製造年」「省エネ性能」などの条件があります。東京スポーツツアー+1
✅ 助成率・上限額・申請期間を把握
-
事業者向け:助成率2/3・上限2,500万円という例あり。条件次第で助成率3/4・上限5,000万円という情報も。株式会社GNE
-
申請期間・募集回によってスケジュールが異なるため、タイミングを見計らって準備する必要があります。東京CO2ダウン+1
✅ 申請前に必要な準備
-
導入前に省エネ診断を受けることが助成率アップの条件になっているケースがあります。株式会社GNE
-
導入設備の仕様・見積書・導入スケジュール・CO₂削減見込みなどを整理しておく必要があります。
-
複数回の募集回があり、予算超過時には抽選となる場合もあるため、申請書類の早めの準備が望ましいです。東京CO2ダウン
✅ エアコン更新時の“押さえどころ”
-
現在使用しているエアコンが古い(例えば製造から15年以上)場合、更新のメリットが大きい。
-
高効率な機種を選ぶことで、補助制度の対象となるだけでなく、ランニングコスト削減にもつながります。
-
空調更新を行う際には、設置スペース・室外機の配置・電源(単相/三相)・配管ルートなども含めて設備・工事費も含めたトータルで検討することが重要です。
4. 活用ステップ(店舗・オフィスで空調更新を検討する場合)
-
現状分析:使用中のエアコンの能力・稼働時間・電気料金・型式・製造年数を把握
-
高効率機種の選定:省エネラベル・統一省エネラベルなどの性能を確認 juutakuseisaku1.metro.tokyo.lg.jp
-
補助制度の確認:対象制度の最新募集要項・申請期間・補助率・対象設備をチェック
-
省エネ診断・計画書作成(必要な場合)
-
見積取得・工事契約・導入設備の発注
-
補助金申請:必要書類を揃えて申請(募集回・締切を確認)
-
工事実施・完了報告:工事完了後、報告書や工事完了届の提出が必要な制度もあります。東京CO2ダウン+1
-
効果確認:導入後の運用状況・電気使用量削減・CO₂削減効果を把握しておくと、次回の更新時にも有利です。
5. まとめ:空調更新は“脱炭素”+“コスト削減”のWメリット
東京都のゼロエミッション関連制度を活用することで、エアコン・空調設備を効率的に更新できるチャンスがあります。
ただし、対象要件や申請期間、補助率・上限額など細かい点も多いため、早めの情報収集・計画・準備が鍵です。
設備更新による省エネ効果は、CO₂削減だけでなく、電気料金の抑制・メンテナンス費用の低減といったメリットも期待できます。
ぜひ、制度を賢く活用して、快適・省エネ・脱炭素な空調環境への切り替えをご検討ください。
無料現地調査・見積依頼はこちら

